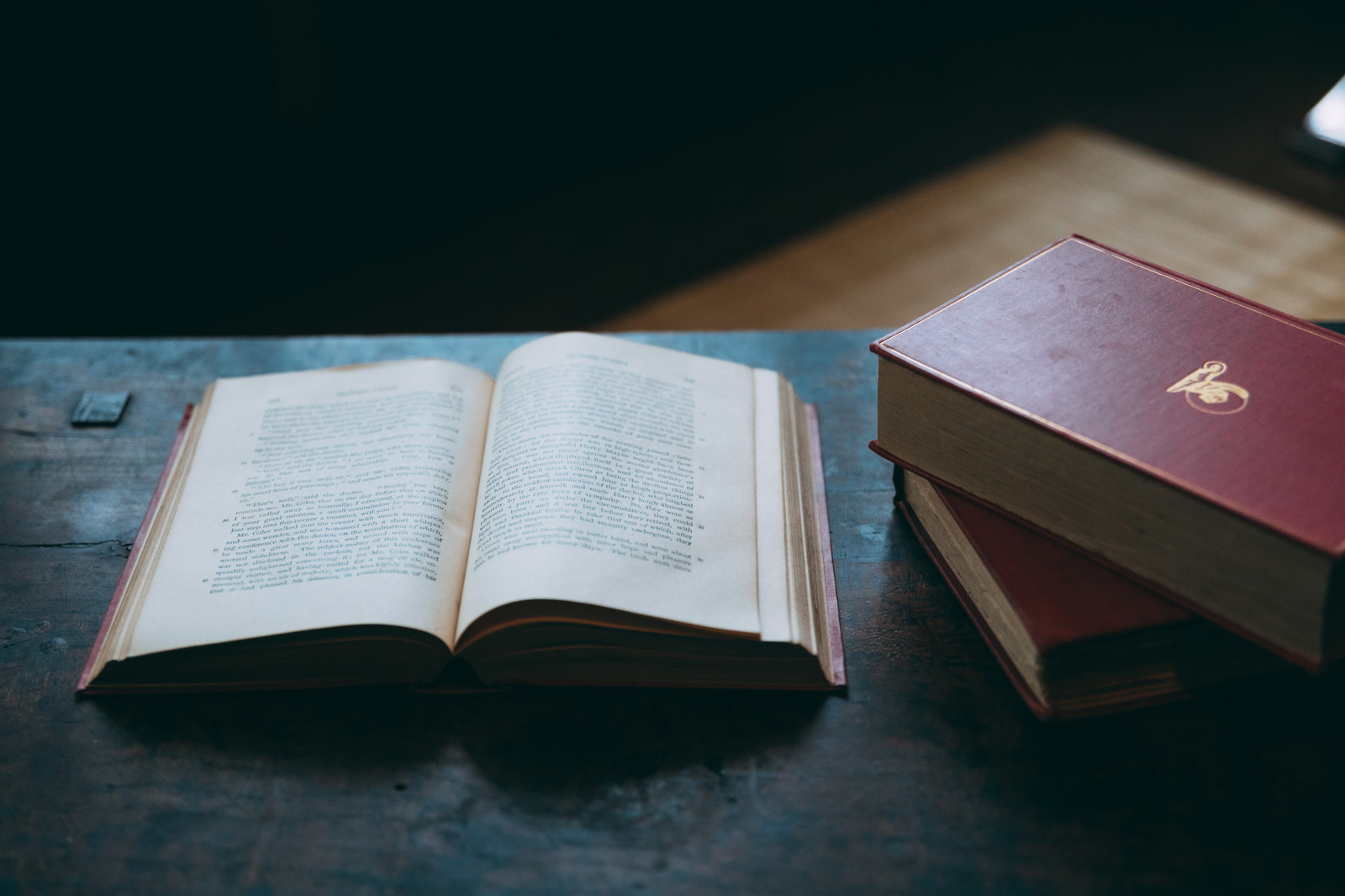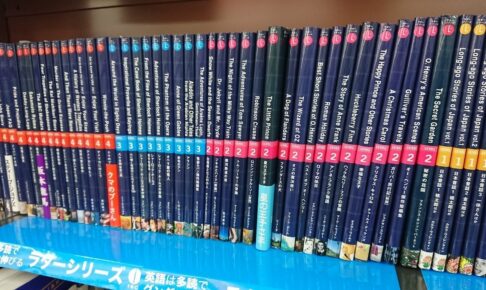どうもフロッキーです。
苫米地さんをご存じでしょうか。知る人ぞしるという感じの方ですが,以下が経歴です。
認知科学者(計算言語学・認知心理学・機能脳科学・離散数理科学・分析哲学)。
カーネギーメロン大学博士(Ph.D.)、同CyLabフェロー、ジョージメイソン大学C4I&サイバー研究所研究教授、早稲田大学研究院客員教授、公益社団法人日本ジャーナリスト協会代表理事、コグニティブリサーチラボ株式会社CEO会長兼基礎研究所長。
マサチューセッツ大学を経て上智大学外国語学部英語学科卒業後、三菱地所へ入社、財務担当者としてロックフェラーセンター買収等を経験。三菱地所在籍のままフルブライト全額給付特待生としてイエール大学大学院計算機科学博士課程に留学、人工知能の父と呼ばれるロジャー・シャンクに学ぶ。
同認知科学研究所、同人工知能研究所を経て、コンピュータ科学と人工知能の世界最高峰カーネギーメロン大学大学院博士課程に転入。計算機科学部機械翻訳研究所(現Language Technology Institute)等に在籍し、人工知能、自然言語処理、ニューラルネットワーク等を研究。全米で4人目、日本人として初の計算言語学の博士号を取得。帰国後、徳島大学助教授、ジャストシステム基礎研究所所長、同ピッツバーグ研究所取締役、通商産業省情報処理振興審議会専門委員などを歴任。
また、晩年のルー・タイスの右腕として活動、ルー・タイスの指示により米国認知科学の研究成果を盛り込んだ最新の能力開発プログラム「TPIE」「PX2」「TICE」コーチングなどの開発を担当。その後、全世界での普及にルー・タイスと共に活動。現在もルー・タイスの遺言によりコーチング普及後継者として全世界で活動中。苫米地式コーチング代表。
サヴォイア王家諸騎士団日本代表、聖マウリツィオ・ラザロ騎士団大十字騎士。近年では、サヴォイア王家によるジュニアナイト養成コーチングプログラムも開発。日本でも完全無償のボランティアプログラムとしてPX2と並行して普及活動中。
プロフィールってこんな書ける人いるんですね(笑)
この記事ではそんな苫米地さんが提唱されている読書法やそれに関連するおすすめの本をまとめます。
苫米地さんの速読術とはどのようなものか
まず苫米地さんが提唱されている読書術の読者の目安を引用します。
(1)読後の理解度のレベルは、これまで通りの速度で読んで理解できていたものと同等のレベルとします。
(2)読書時間は初期目標として6倍速をめざします。
(ほんとうに頭がよくなる「速読脳」のつくり方より)
このように苫米地さんの読書はまず速読ありきです。
その際に速読するのだが速読してもなお「ちゃんと文字を追って速読する」ことを提唱されています。
そして苫米地さん推奨する読書冊数は「1か月最低100冊」。ということは一日に3冊読む計算ですね。さすがに海外の一流大学に留学されていただけありますね。
(しかもできれば英語の本を読むことを推奨されていますが,ここでは日本語の本の速読法についてまとめます。)
趣味の本を速読する必要はないため、必然的に「知識を得るための読書」で1か月100冊を目指すことになります。
ただ苫米地さんが指摘されてることで一番重要なことは
速読するためには「読む前の知識量」が重要になるという事実です。
つまりより多くのことを知っている人は早く読めるということです。
確かに僕は英語多読をやっていますが,英語の本を読めば読むほど早くなってる実感はありますね。
苫米地さんの人生の中で相当な数の本を読まれてきたでしょうね。茂木さんの読んできた洋書をまとめましたが,相当な読書量でした。知識人は偉大ですね。
卵が先がにわとりが先かの話のような・・・。ただ今日から新ジャンルの本に挑戦すればどんどん早くなるということなので,僕は意外とポジティブですね。
今回の記事をまとめにあたっての参考文献は以下の四冊ですが,「速読脳の作り方」が一番おすすめですね。
それでは「読むべき本と読まなくてよい本を選ぶ2種類の読み方」を見ていきましょう!
読むべき本と読まなくてよい本を選ぶ2種類の読み方
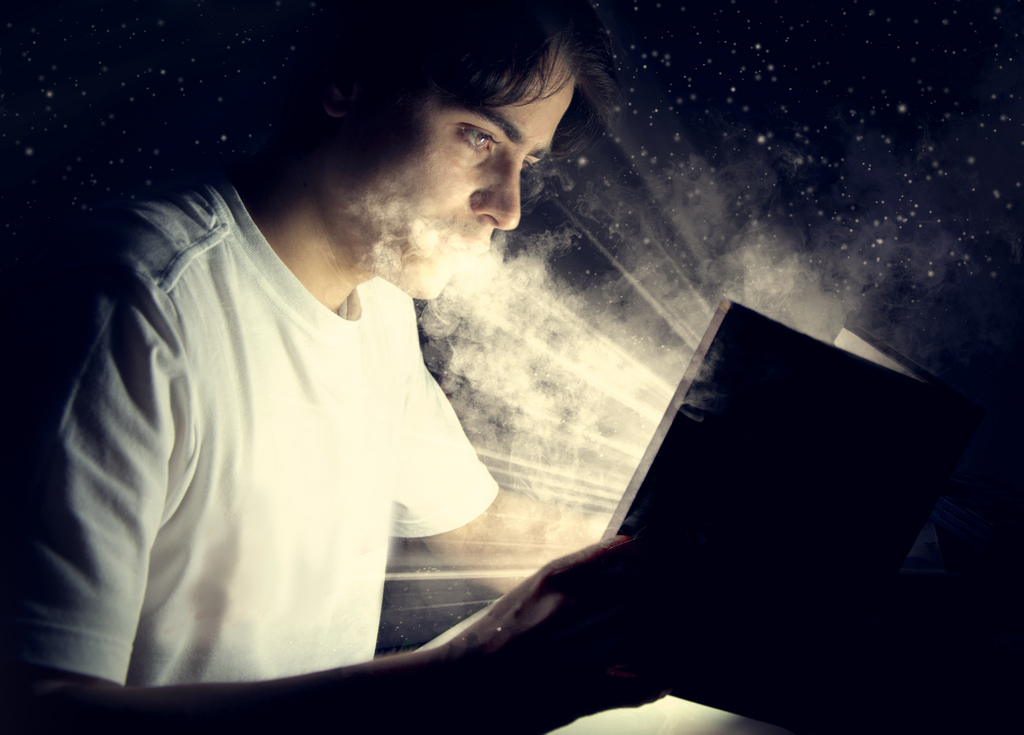
大前提として
1.読むべき本を探す時
2.実際の知識を仕入れる時
の速読法は分ける必要があります。
言ってみれば1は書店で探すとき、2は本を買ってきて家で読む時に使うということですね。
読むべき本を探す時
この場合は
「キーワードを決めて速読する」
という従来の速読法が有効だそうです。速読というとこのキーワードリーディングのイメージがありますよね。
ただこの方法は自分の知識に頼ってしまうので,危険な方法でもあります。(以下で説明します)
ではなぜそんな方法が書店で探すときには使えるのかというと
自分にとって必要な本というのは、現在の自分の知識の周辺事項について書かれている本だからです。
例えば石原慎太郎氏の『天才』を読んだ後の周辺事項というのは日本の政治について、田中角栄の具体的な政策、他の政治家との違いなどが気になりますよね。
このように僕たちは,自分の知っている知識をもとに新たな知識を勉強します。
まあある程度読書している前提ですが,自分の周辺知識で知りたいことを思い浮かべながら書店で立ち読みすれば効率的ですね。
(読書初心者でも使える方法は次の次の章で紹介します!)
実際に知識を仕入れる時の読み方
次に、実際の知識を仕入れる時に用いる方法は
著者になりきって速読する
というもの。ここで先ほどの速読と違う点は、さっきは自分中心で速読しましたが今度は他人になりきるという点です。
なぜ自分を主体で知識を仕入れるときは読んではいけないのでしょうか。
それは、自分の知識を主体に読んでしまうと自分の知らない知識は見えてこなくなってしまうからです。この見えなくなることをスコト―マといいます。
さっきの自分の知識の上に新たな知識を乗せる,という方法に矛盾するようで実はしていなくて
つまり自分の知識,自分の読書ゴール(金儲け,速読したいなど)にとらわれすぎると,意外と大切な周辺知識が見えなくなってしまうということです。
例えば「俺は速読する方法だけ知りたいんだ!」と自分主体で読書してしまうと、速読する方法しか見えてきません。
本来自分に必要なその他の情報が見えてこなくなってしまうわけですね。
そうならないためにもまず著者紹介の部分を読んで、著者がどのような人なのかを想像して「この著者の主張は何を伝えたいのか」と著者になりきれば
自分が何を知りたいなど,自分の欲とは別に客観的に文章が読めるので
自分の知らない知識も著者にとって重要なものが見えてくるということです。
この著者にとって重要なものは今後の自分にとっても重要な可能性が高いです。だいたいは自分よりも知識がある人が本を書いてますからね!
ただそうはいっても,「前提知識が少ない読書初心者はどうすればいいんだろう」となりますよね。
次では読書初心者のための本の選び方をまとめます。
読書初心者必見の本の選び方
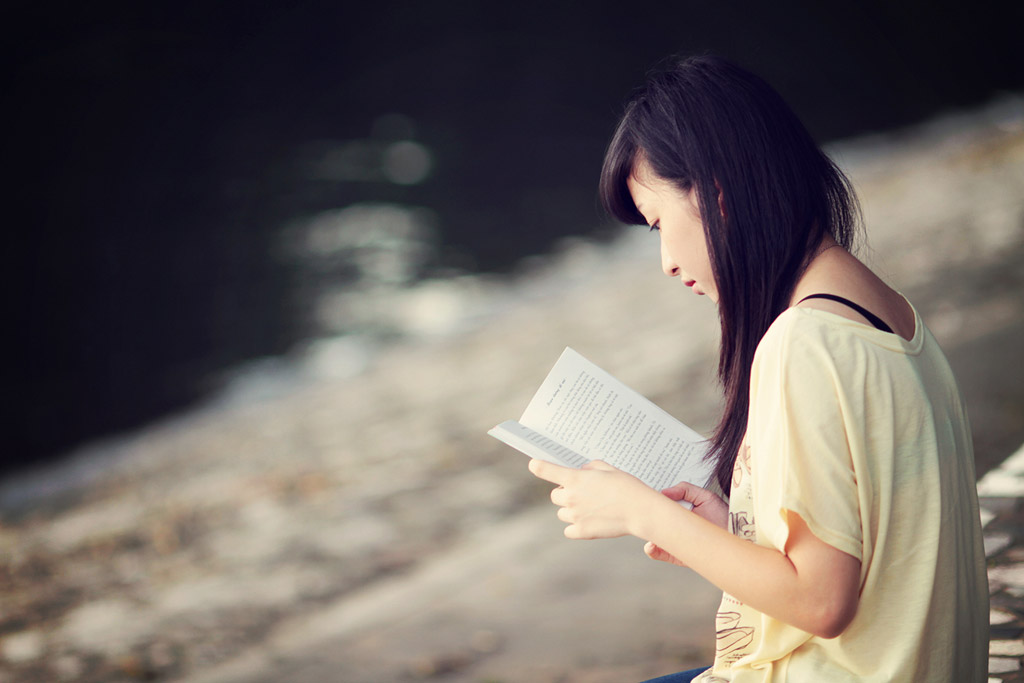
さきほど紹介した著者になりきるということからも分かるように、自分に重要な情報というのは、自分の外にある可能性が非常に高いです。
以下の本の中でも
「人間が認識できる光の範囲ですら、それ以外に観測されている領域のほんの一部分にすぎないから、重要なことは自分の外にある確率の方が圧倒的に高い」というエピソードが描かれています。
確かによく考えてみれば自分が知っていることなんてたかが知れていますね。今はChatGPTがなんでも教えてくれる時代ですからね。
しかも読書を始めたての頃は本当に何も知らないから、ついつい自分が好きな、同じような分野の本を選んでしまう傾向があります。
そこで苫米地さんおすすめの方法として
「アマゾンのランキング上位100を片っ端から読む」
というものがあります。
ここで対象になる本は小説、それ以外の趣味に関する本は除外したランキングです。紀伊国屋などのランキングでも可能とのこと。
僕もこの方法を実践しましたが,自分では全く読まないであろう本を読むのもまた面白いですよ(笑)。
『天才』を読めば政治のことがもっと知りたくなるし、『蒼い時』を読めば山口百恵の歌が聞きたくなるという具合ですね。
またこれは派生ですが
「過去のベストセラーを読む」
という方法も有益だと思っています。
「アマゾンのランキング上位100を片っ端から読む」
「過去のベストセラーを読む」
どちらともいえるのは自分の軸で選んでいないということです。
初心者のうちが全く知識がない状態なので,自分の関心ではなくあえて世間の関心から知識を選ぶのが重要ではないかと,苫米地さんは指摘されています。
まとめ
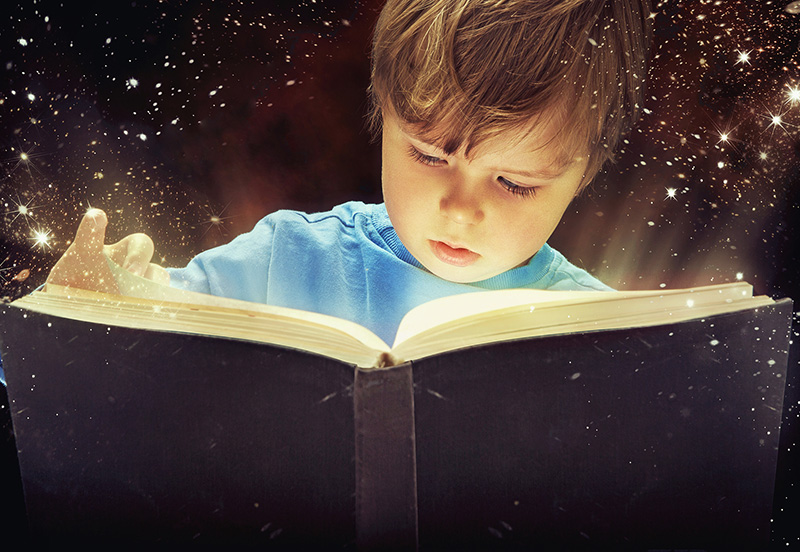
苫米地さんの読書法をまとめてみました。
つまるところ自分にとらわれるな!と仏教的な読書法だったなと感じます。
この記事ではそれぞれの一部分を紹介という形になったので、それぞれの本を読んでいただければより理解が深まると思います。