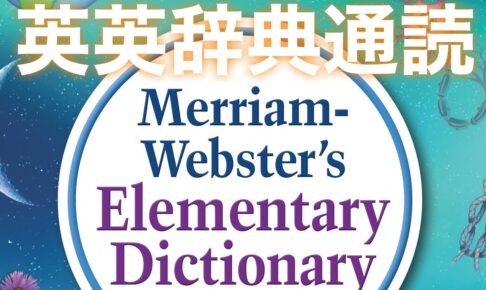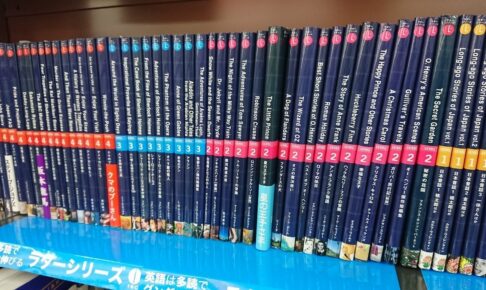どうもフロッキーです。
みなさんは宮台真司さんをご存じでしょうか。
切りつけ事件に関しては驚きましたが,それ以前から有名な方でした。プロフィールはこちら。
1959年3月3日、宮城県仙台市生まれ。私立の名門、麻布中・高校卒業後、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。社会学博士。大学院在学中からサブカルライターとして活躍し、女子高生のブルセラや援助交際の実態を取り上げ、90年代に入るとメディアにもたびたび登場、行動する論客として脚光を浴びた。その後は国内の新聞雑誌やテレビに接触せず、インターネット動画番組「マル激トーク・オン・デマンド」や個人ブログ「ミヤダイ・ドットコム」など自らの媒体を通じて社会に発信を続ける。著書は『日本の難点』(幻冬舎新書)、『14歳からの社会学』(世界文化社)、『〈世界〉はそもそもデタラメである』(メディアファクトリー)など多数ある。
そんな僕たち飽き性の星のような方ですが,宮台さんもかなりの飽き性,ADHDということで変わった勉強法をされていたそうです。
その勉強法によって全国模試総合1位を取ったこともあるそうです。
それで浪人することになって駿台高等予備校に入ったのですが、高3最後の1月模試で38だった世界史の偏差値を、3ヶ月後の4月模試では72まで上げました。以降、そのノウハウを使ったところ、駿台の全国模試の全てで成績優秀者ランキング入りしました。全国模試総合1位を取ったこともあります。
(以下この記事から引用します)
もちろん宮台さんのスペックということもあると思いますが,飽き性の我々にも参考になることがあるはずです。どんな勉強方法なのか気になりませんか!
今回はその宮台さんの勉強方法についてまとめます。いっしょに見ていきましょう。
宮台真司の飽き性流勉強法とは
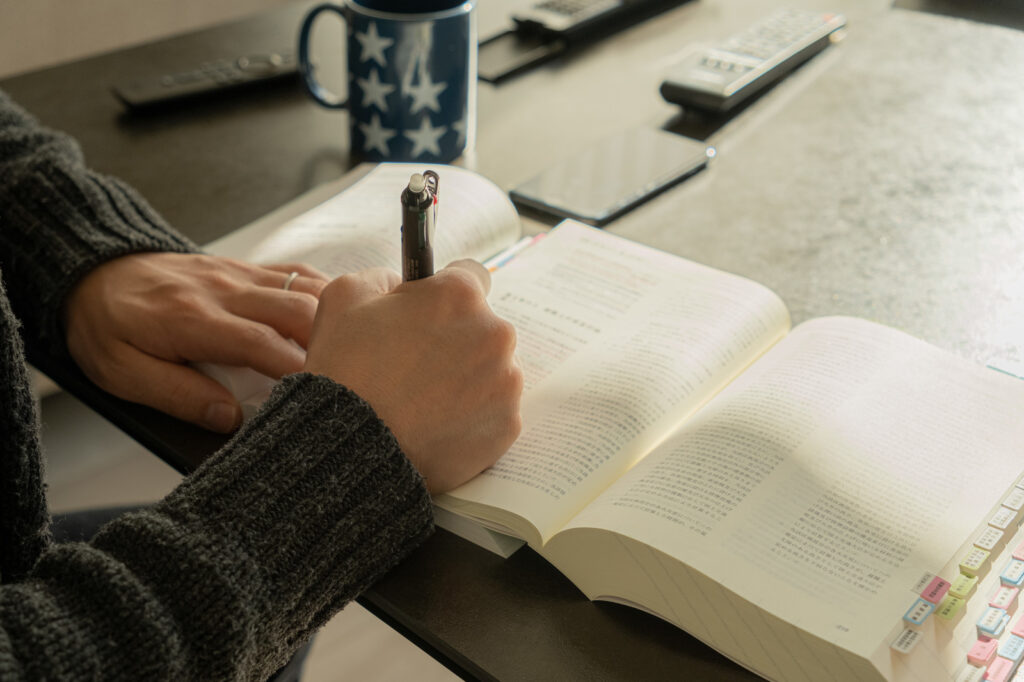
僕は飽きっぽくて集中力が続かなくなる性質なので、1科目10分間で区切ることにしたんです。東大は5教科7科目だから、デスクに7冊の問題集を置き、タイマーをセットして、最初の科目は10分経ったら必ずやめて、次も10分、次も10分……と、短冊式に何度もぐるぐる回る。同じ科目を約1時間に1度必ずやるわけです。
オーソドックな勉強法は,英語60分→休憩→数学60分→…とやっていくパターンだと思いますが,宮台さんの場合は10分で区切っていたそうです。
確かに我々飽き性は最初の瞬発力はありますよね。ただそれが60分も続かないんです。僕も20分くらいで飽きてきてます。
ただ目新しいことの最初は集中できるので,その特定を生かした勉強法ですね。
この勉強法で短時間の勉強にかかわらず偏差値70台をキープされていたようです。
僕は、予備校時代も自宅では1日4時間以上は勉強しないと決めて、1か月に30本以上の映画を見ていました。それでも偏差値70台を問題なくキープできました。10分単位のローテーションで集中力を持続すれば、受験程度のことは暗記だけでクリアできるからです。
このように飽き性の人は細切れがキーワードですね。
僕もウーバー配達中の待ち時間に英英辞典を通読したり,トイレで洋書を読んだりしてます。
あとは場所もコロコロ変えながら勉強していますね。
まとめ
孫氏が言ったようにやはり「彼を知り己を知れば百戦殆からず」ですね。
集中力が持たないとはいいますが,それは言い換えれば短期間なら集中できるということ。
その特性を生かして宮台さんは東京大学に入学され,今もなお活躍されているんですね。
何か集中力が持たないというのはダメなことのように思っていましたが,大きな誤解だったようです。
皆さんも自分を生かした方法で勉強や情報収集を考えていきましょう!