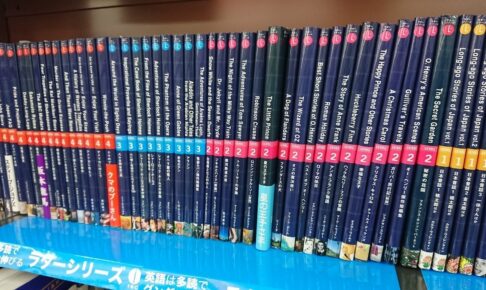どうもフロッキーです。
「働きアリってみんな働いてるでしょ?そんな奴いたら村八分にされるんじゃないの?」
と僕も最初思っていました。しかし,アリなりの賢い戦略によってあえて働いていないアリが存在するようです。
結論としてはかなり面白くとても考えさせられる本でした。
面白かった点はたくさんありますが、一番重要な働かないアリの存在意義について今回はその点だけに絞って書きます。
漫画版もあるようです。
本の目次
序章 ヒトの社会、ムシの社会
第1章 7割のアリは休んでいる
第2章 働かないアリはなぜ存在するのか?
第3章 なんで他人のために働くの?
第4章 自分がよければ
第5章 「群れ」か「個」か、それが問題だ
終章 その進化はなんのため?
※大見出しのみ
働かないアリが絶対に必要な理由

アリのコロニー生存戦略として必要だからです。
みんながシャカリキになって働いてしまうと,災害が起きたときに対応できるアリがいなくなってしまいますよね。
みんな疲れていていざという時に動けない。これはコロニーにとって一番避けなければいけないことです。
この予備軍として「働かないアリ」が準備しているわけです(笑)
作者は,個々のアリの反応閾値の違いで説明しています。
反応閾値とは
刺激に対して行動を起こすのに必要な刺激量の限界値
とある。本文の例が分かりやすかったので第2章の61ページの一部を引用します。
人間にはきれい好きとそうでない人がいて、部屋がどのくらい散らかると掃除を始めるかが個人によって違ってきます。きれい好きな人は「汚れ」に対する反応閾値が低く、散らかっていても平気な人は反応閾値が高いということができます。要するに「個性」と言い換えることもできるでしょう。
部屋を片付ける例は分かりやすいですね。僕は部屋の片づけの閾値が他の家族より明らかに高いです(笑)。全然汚いと思いませんね。
まあそれも相対的な話ですけどね。ゴミ屋敷ほどにはなりません。
この閾値がアリにも存在するということです。
仕事をしようと動き出す基準にアリごとにあることによって,コロニー内の多様性を生んでいるということです。賢いですね。
例えば今アリたちにとって必要な仕事は、閾値50までのアリで足りているとします。
だけど自然災害などによって多くの閾値50までのアリが死んでしまうと、仕事が回らなくなってくる。
すると巣の中が汚れてきたり、エサが不足したり、なめてもらえてない幼虫が出てきます。
※幼虫を定期的になめないと、細菌が繁殖してしまい、幼虫は死ぬ。唾液で消毒しているのだ。幼虫が死ぬということは次世代のワーカーを失うわけだからアリ社会には致命的です。
すると今まで働いていなかったアリたちが仕事に気付くようになります。人間でいうと部屋が汚くなってきたことに感じですね。
こうして今まで働いていなったアリたちが,出動している間に幼虫が成虫になったり,今まで働いていたアリたちが温存できるわけです。
そしてコロニー内が正常に戻ったら,「働かないアリ」たちはまたボーとします。この繰り返しでコロニーを生存させるわけです。

この仕組みはすごいですね。
実際にコンピュータのシュミレーションでは全員が働くコロニーは一時的な生産量は多いそうですが、長期的な存続率は働かないアリがいるコロニーの方が高いそうです。
全員が働いてしまうことによって,災害時にみんな動けなくて結果的に生産性が下がるのでしょうね。
人間社会にも言えることかもしれませんね。
しかもこの仕組みは,別々のコロニーの働きアリだけを集めたコロニーを人工的につくってみると、働かないアリが誕生するそうです。
みんな働いていたはずなのに!
やはり相対的な話なので,周りにより多く働くアリたちがいれば,元働きアリは温存しようと思うようですね。面白い!
まとめ
このほかにも、
- お馬鹿なアリがいた方がいい理由
- 女王アリだけが出産する理由
- システムを利用する裏切り者(チーター)について
- 自分の安全のために交尾中にオスの腹を嚙み切るメスの話
など面白い話がわんさか出てきます。
群選択やDNAの関係についてなど難解な部分もありましたが、それ以外の部分はとても面白いですよ。
タイトルに興味を持った人にはぜひおすすめします。